求人を出しているのに応募が伸びない、良い人が来ない、早期離職が続く。
そんな時にまず見直したいのが「採用サイトの有無と中身」です。求人媒体は入口として有効ですが、応募直前の“安心・納得”は公式の採用情報で担保されるケースが増えています。採用サイトがない(あるいは情報が薄い)状態は、比べられる土俵に乗り切れていない可能性さえあります。
自社の採用サイトを短期間で作りたい方へ→採用サイト制作サポート
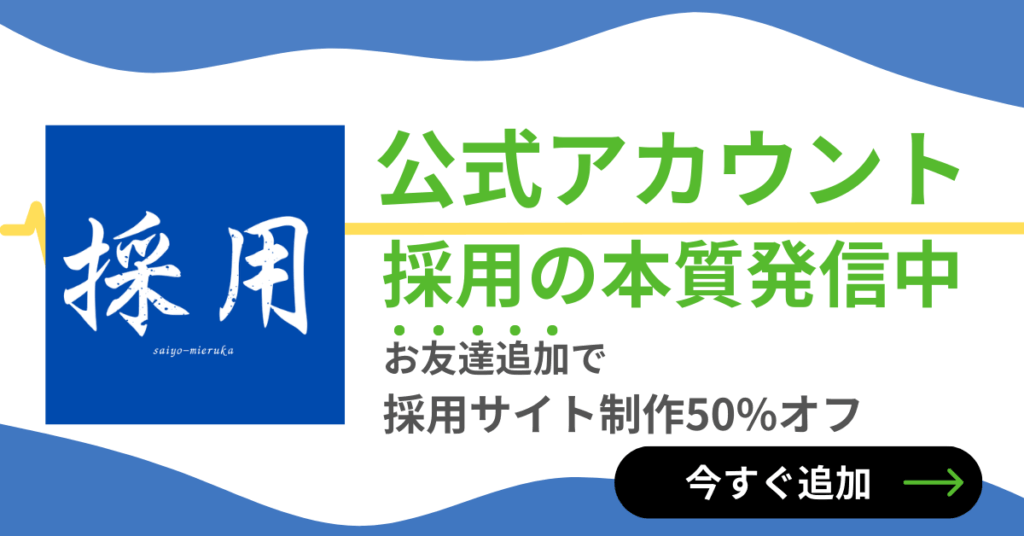
なぜ無いとまずいのか?
採用活動において、採用サイトはもはや「あると便利」なものではなく、「あって当然のインフラ」になりつつあります。求職者は、給与や職種名といった定型情報を求人媒体でインプットした後、必ずと言っていいほど「その情報が真実か」「自分に合っているか」という最終確認のプロセスに入ります。
複数の調査結果が示す通り、多くの求職者が応募前や入社決定前に企業の採用サイトを訪問しています。
特に若年層ではより高く、67%の求職者が「応募前に企業の採用ページを必ず訪問する」と回答。
出典:求職者の7割が応募の決め手にしている採用サイトってなに?|https://relative.company/info/1788/
「入社を決めた会社について」と条件を絞った上で採用サイトの利用動向を調査した結果、60.99%が「(採用サイトを)見た」、39.01%が「(採用サイトを)見なかった」という回答が得られました。
出典:中途採用における採用サイト利用実態調査(2024年度版)|https://baigie.me/recruit-blog/2024/10/09/midcareer-survey-2024/
最終的に入社を決めた企業について、就職活動中に採用サイトを閲覧した学生は81.92%に上りました。
出典:求職者が求める採用サイトの役割について|https://www.hrpro.co.jp/press_detail.php?ccd=01465&press_no=1
これらのデータは、採用サイトが事実上の「一次選考の場」になっていることを示唆しています。求人票で興味を持ったとしても、採用サイトで企業の信頼性、文化、社員の顔が見えなければ、求職者は不安を解消できず、応募を躊躇してしまいます。
採用サイトがない、または情報が薄い企業は、この「応募直前の心理的なハードルを下げるチャンス」を逃していることになります。他社が魅力的な情報提供をしている中で、比較検討の土俵にすら上がれず、優秀な候補者を静かに失っている可能性が高いのです。
比較検討の材料となる採用サイト制作→採用サイト制作
何を見られているのか→働くイメージの具体化
求職者が採用サイトで知りたいのは、単なる企業のカタログ情報ではありません。「自分がこの会社で働く1日」や「3年後の自分」を具体的にイメージするための材料です。
ある調査では、応募検討時に採用サイトで知りたい情報の上位として、以下の項目が挙がっています。
応募検討時に企業の採用サイトで知りたい情報の1位は「仕事内容(85.7%)」となった。2位は「福利厚生制度(70%)」、3位「昇給や給料等の待遇(69.1%)」と続いた。
出典:採用サイトで知りたい情報は仕事内容・職場環境といった「働くイメージ」|https://hrzine.jp/article/detail/4879
ここで重要なのは、1位の「仕事内容」が、求人媒体に書かれている抽象的な職務記述書とは異なるということです。求職者が求めているのは、以下の解像度の高い情報です。
- 仕事のリアリティ:職種ごとの具体的な一日の流れ、関わるプロジェクトの事例、使用しているツールや開発環境など。これにより、「自分にこの仕事ができるか」の判断と「入社後のギャップ」の解消を図ります。
- 待遇と安心感:福利厚生や昇給・給与体系といった「待遇」は、企業が社員の生活や成長をどう考えているか、という社員への姿勢を測る指標です。明文化されていれば、長期的なキャリアプランを描きやすくなり、安心して応募へと進むことができます。
つまり、採用サイトは、求人媒体では伝えきれない「働くことのリアル」と「安心感」を提供し、候補者の意欲を動機付けるための場所なのです。
“求人だけで勝負”の限界:入口と評価は別物
求人媒体への出稿は、多くの求職者に自社の存在と求人情報を知らせる「集客(入口)」としては非常に有効です。しかし、求人媒体と採用サイトは、採用プロセスにおいて異なる役割を担っています。
求職者の8割が企業サイトを訪れる一方で、直接応募する割合はわずか4.9%。
出典:採用成功の分かれ道?8割の求職者が企業サイトで確かめていること|https://www.rshd.co.jp/work/saiyou_knowledge-4.html
このデータは、「求人を見た人がそのまま媒体で応募する」のではなく、「求人媒体で知る → 採用サイトで評価する → 応募する」というステップを踏んでいることを示しています。
求人媒体は、さまざまな企業の求人が並ぶ「ショッピングモール」のようなものです。候補者は多くの選択肢の中で、まず「知る」という行動を取ります。一方、採用サイトは企業の「独自店舗」です。ここでは、企業の世界観、働く人々の顔、独自の文化といった、他社との差別化要素を最大限に訴求できます。
直接応募の割合が低いのは、候補者が情報収集を終えた後、媒体を経由して応募したり、エージェント経由で応募したりする流れが一般的であるためです。重要なのは、採用サイトが「応募の質を高める」ことに貢献している点です。
採用サイトをしっかりと作り込むことで、企業文化や価値観に共感した「口説かれている状態」の候補者からの応募が増え、結果として面接通過率や内定承諾率の向上、さらには早期離職の防止へとつながるのです。
勝てる採用サイトに載せるべき要素
- 仕事理解が深まる情報(職種別の一日、プロジェクト事例、使用ツール)
- 人と文化が伝わる要素(社員インタビュー、行動指針、写真・短尺動画)
- 不安を解消する明文化(待遇・福利厚生・評価制度・教育体制)
- 短い応募導線(職種LP → Q&A → エントリーの最短導線とフォーム最適化)
- 媒体連携を前提とした計測(Indeed/求人ボックス/SNSからの遷移をUTMで可視化)
まとめ:まずは自社の“見える化”から
採用サイトがない状態は、応募前の最終確認を失いやすく、比較で不利になりがちです。採用サイトは、求人媒体という入口(集客)と、応募の質を高める評価(動機付け)をつなぐハブの役割を果たします。
とはいえ、採用サイトを制作会社に頼んだら高額になりますし、自社でやるとどうしても時間がかかりすぎたり、内容に偏りが出やすくなります。そういった時に活用すべきなのが、ノーコードのSTUDIO。弊社でも開発している採用サイトテンプレートを土台に短期で立ち上げ、公開後に写真・動画・記事を随時足していく運用が可能です。これなら、初速を出しつつ、採用の“自社メディア”として拡張していけます。
応募の量と質、そして定着までを設計するために、まずは自社の「働くリアル」を可視化し、採用サイトという資産を構築しましょう。
採用サイト制作に興味がある方は、まずは無料でトップページのサンプルを作成いたします。→採用サイト制作サービスはこちら
※正式制作にあたっては、プロによる写真撮影、動画撮影、貴社の強みをインタービューした上での最適な発信手法をご提案します。
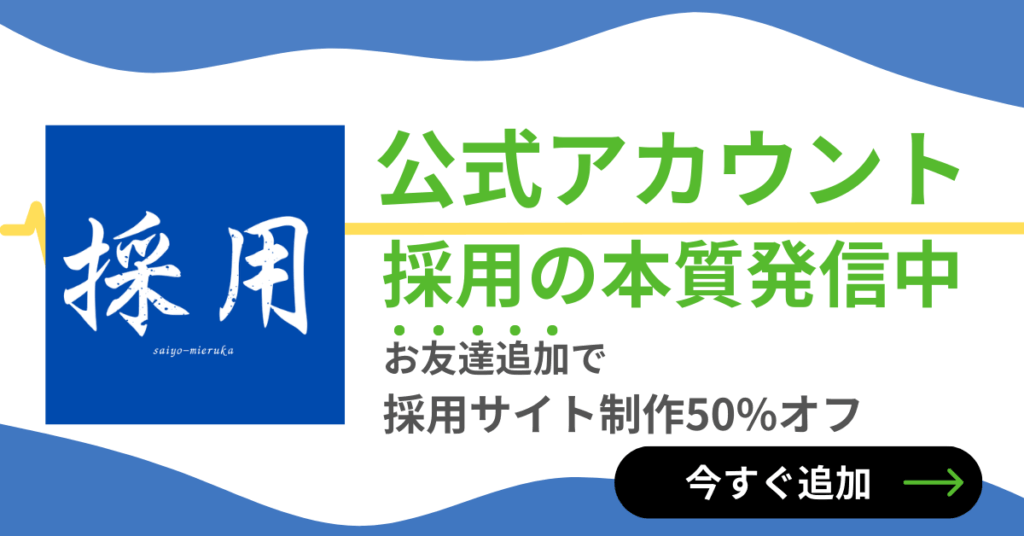
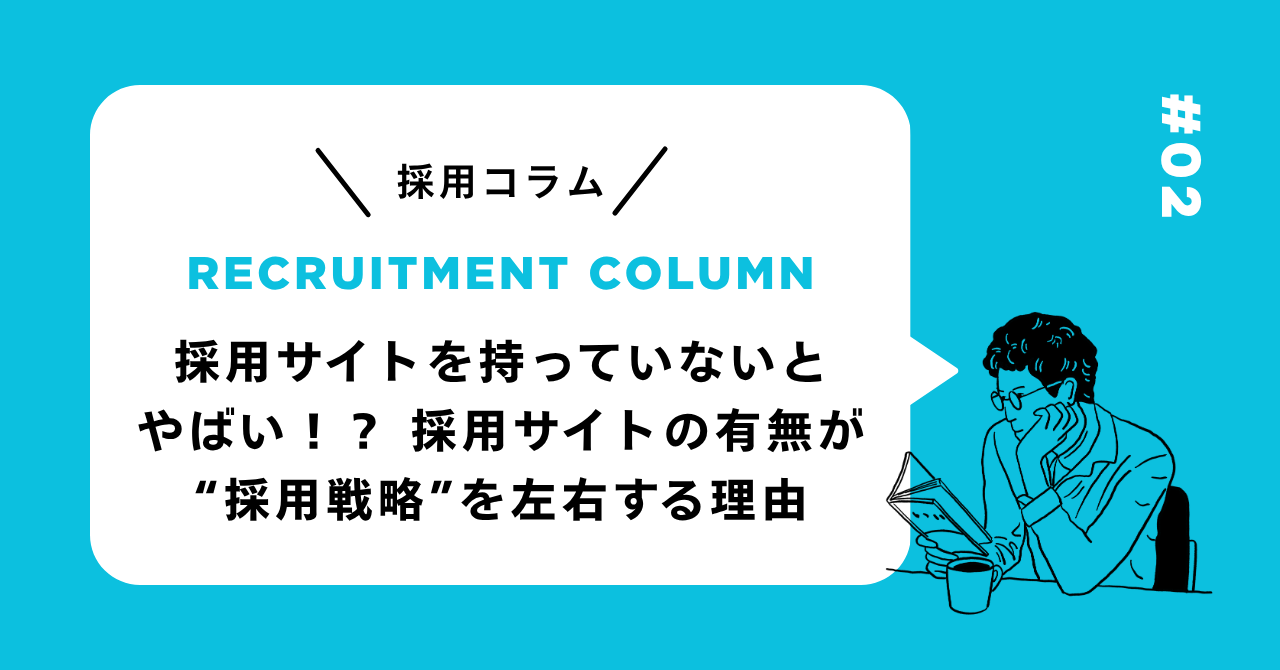
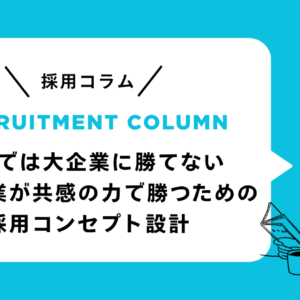
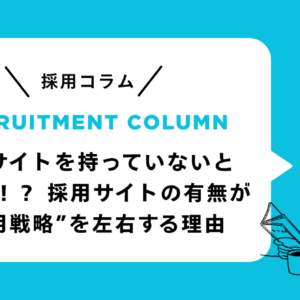
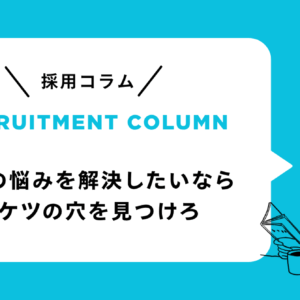
コメント