2024年4月1日施行の改正で、求人広告や採用サイトの募集時に明示すべき労働条件が追加され、あわせて雇入れ時の労働条件通知の必須項目も拡張されました。本記事は中小企業の実務担当向けに、何を・どこまで・どう書くかを最短で整えるチェックリストとサンプル文をまとめたものです。
令和6年4月1日から、募集時に①従事すべき業務の変更の範囲、②就業の場所の変更の範囲、③(有期)更新基準と更新上限の明示が必要になります。
雇入れ時の労働条件通知も改正され、雇入れ直後+変更の範囲の明示、(有期では)更新上限・無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示が必要です。
まず押さえる:募集時と雇入れ時の違い
募集時の明示(職安法)は不特定多数に示す求人情報(採用サイト・媒体)に適用、雇入れ時の明示(労基法)は採用確定者へ交付する労働条件通知書に適用されます。今回の改正は両方に影響するため、採用サイト/媒体/通知書の三点セットで文言の整合を取りましょう。
【募集時】採用サイト・求人広告で必ず示す項目
- 従事すべき業務(雇入れ直後)
- 業務の変更の範囲(例:事務系業務全般/変更なし 等)
- 就業の場所(雇入れ直後)
- 就業の場所の変更の範囲(例:東京都内各拠点/転勤なし 等)
- 就業時間・休憩・休日・時間外労働
- 賃金(総額・内訳・手当・賞与、固定残業の有無と時間数)
- (有期)契約期間、契約更新の基準、更新上限(通算期間/回数)
- (推奨)試用期間の有無・期間・待遇
NG→OKの記載テンプレ
業務の変更の範囲
NG:「適宜変動あり」「会社の定める業務」
OK:「総務・人事・庶務の範囲で配置転換の可能性あり(専門外への変更は原則なし)」
就業場所の変更の範囲
NG:「全国転勤あり」
OK:「東京都23区内の各拠点間。原則、県外転勤なし」
(有期)更新上限
NG:「あり」だけの記載
OK:「通算3年(更新回数上限3回)。新設・短縮時は事前に理由を説明」
根拠:無期転換サイト:更新上限・説明の要件
【雇入れ時】労働条件通知書の追加・強化ポイント
- 業務・就業場所の「雇入れ直後」と「変更の範囲」を併記
- (有期)契約期間、更新の有無・基準、更新上限
- (有期)無期転換申込機会、無期転換後の労働条件(均衡配慮事項の説明努力)
- 試用期間の有無・期間・待遇
- 就業時間・休憩・休日・時間外(36協定の有無等)
- 賃金(総額・内訳・締め日・支払日、固定残業の有無と時間数)
モデル様式:各地労働局の配布ページ例(滋賀労働局:モデル通知書(令和6年4月以降))
媒体・職業紹介・採用サイトでの運用ルール
- マスター原稿の一本化:社内承認済みの「募集時マスター」を作成し、媒体・自社サイト・職業紹介へ同文言で展開。
- 範囲表現の辞書化:「都内各拠点」「事務系業務全般」など曖昧語を排除した定型句を用意。
- 有期の更新基準は列挙:業務量/勤務成績/会社業績 等の判断要素を明文化。
- 固定残業の透明化:対象時間・超過時の割増支給・見直し時期を明示。
- 改定ログの表示:求人ページ末尾に「最終更新:YYYY-MM-DD」を記載。
【コピペ可】募集時表示のサンプル文
業務の変更の範囲:総務・人事・庶務の範囲で配置転換の可能性があります(専門職から事務職への変更など、職種の大幅な変更は原則ありません)。
就業場所の変更の範囲:本社および東京都23区内の各拠点間で異動の可能性があります(県外転勤は原則なし)。
(有期)更新の基準:業務量、勤務成績、勤怠、会社の経営状況、担当業務の継続性等を総合的に勘案して判断します。更新上限:通算3年(更新回数上限3回)。
採用サイト実装:CMS/テンプレの直し方
- 入力フィールド追加:「業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「(有期)更新上限」を独立項目にし、必須化。
- UIガイド:プレースホルダに具体例、曖昧語(応相談/適宜等)を検知したら警告。
- ページ末尾の注記:「本ページは募集時の条件です。最終条件は労働条件通知書にて確定します」。
チェックリスト抜粋(募集時)
- 従事すべき業務(雇入れ直後)/変更の範囲の具体記載
- 就業場所(雇入れ直後)/変更の範囲の地理特定
- (有期)更新基準を列挙し、更新上限を明示
- 賃金は総額・内訳・固定残業時間数を明示
フル版はExcelテンプレをご利用ください:job_ad_disclosure_checklist.xlsx
参考:一次情報リンク
- 令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(厚労省)
- 令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります(厚労省)
- 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(無期転換サイト)
- 労働条件通知書モデル様式(令和6年4月以降)
免責
本記事は公開時点の公的資料に基づく一般的な情報提供です。個別の案件や就業規則との整合は、社労士など専門家にご確認ください。
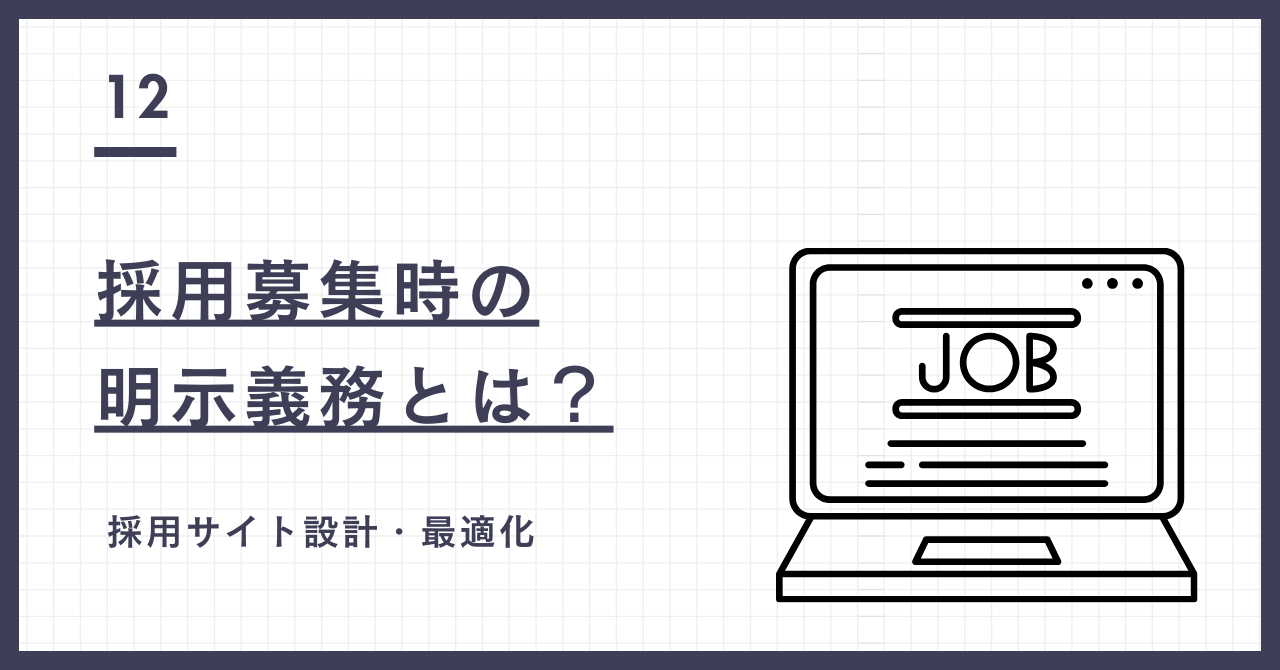
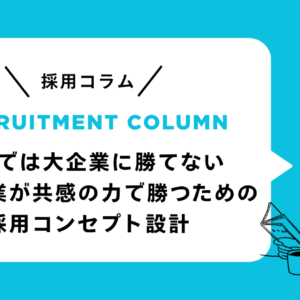
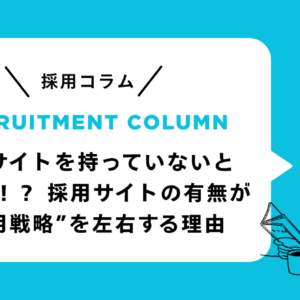
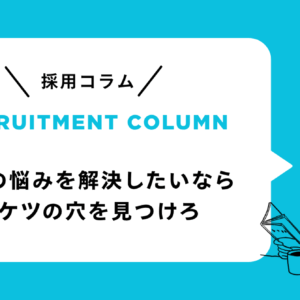
コメント